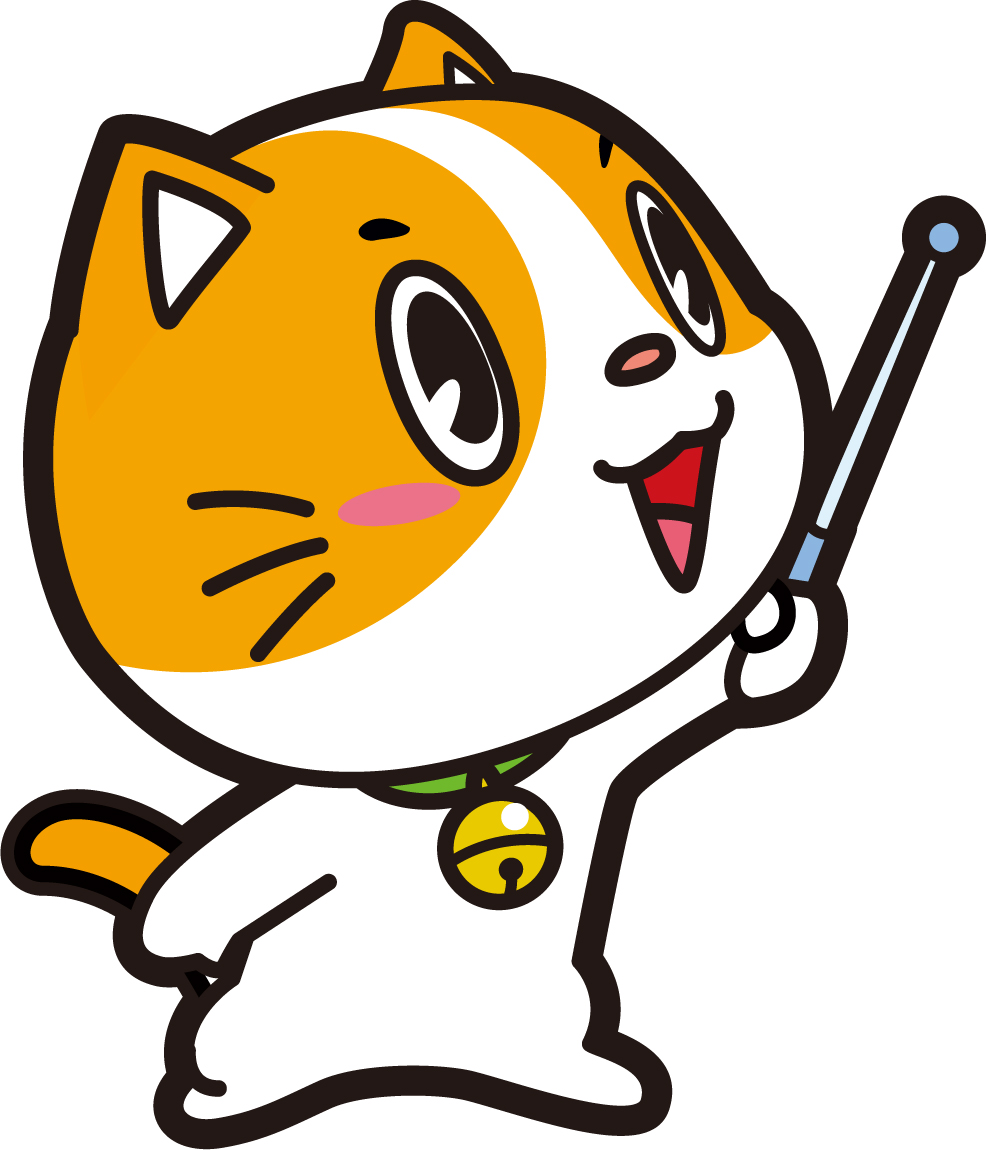夏になると行事やイベント事が多くなってきますが、8月にはお盆があるのをご存知でしょうか?
実際、今までお盆の期間や何をするのかなど、深く考えたことも気にしていなかった人もいるかと思います。
この記事では、お盆の期間や何を行うのかを解説していきます。
記事の内容
お盆とは?

お盆の意味
お盆は、祖先や亡くなった人たちがこの世にさまよって苦しむことなく、成仏してもらえることを願って、子孫が追善や報恩の供養をする期間のことを意味しています。
お盆の正式な呼び方は、盂蘭盆会(うらぼんえ)と言って、諸々の説が存在していますが、サンスクリット語で逆さ吊りを示すウラバンナの音写であるとする説が有力とされ、先祖の霊を招き寄せ供養する恒例行事として全国的に広く行われています。
自分に関係のある身近な人が亡くなられて四十九日法要が終わってから一番最初に迎えるお盆を初盆(はつぼん)あるいは、新盆(しんぼん、にいぼん、あらぼん)と呼び、家の玄関やお墓に真っ白の提灯を立て、初盆以外のお墓には白と赤の色が入った提灯を用意して立てるなど、特に手厚く供養する慣習があります。
初盆には四十九日や一周忌、三回忌などの食事を交えた法事法要とは別に、法要として供養の儀式が行われますが、一般的に初盆を過ぎたお盆は身内だけで先祖の霊と共に供養をします。
お盆の由来
お盆の由来として、日本では推古天皇14年(西暦606年)に、お盆の行事が初めて営まれたと言われています。
全国各地で行われているお盆の恒例行事は、各地域の慣習などが加わったり、宗派による違いなどによって多種多様ですが、一般的に祖先の霊がこの世に帰ってくると考えられています。
お盆の期間はいつ?

昔のお盆の期間
昔のお盆の期間は、当時ではお盆に行われる行事が旧暦の7月15日を主として、7月13日~16日がお盆の期間とされていました。
そもそも、お盆の行事は7月に行われていたとのことですが、お盆の慣習の起源は非常に古く、平安時代には盂蘭盆会(うらぼんえ)の行事が浸透していたと言われています。
そして、明治時代を過ぎてから、新暦(太陽暦)が適用されて一般化されたことにより、8月のお盆が誕生し、3つの時期に区別されていきました。
以下に、3つのお盆の期間を簡単にまとめました↓↓↓
- 7月13日~15日
→旧暦の月日がそのまま新暦に残ったため - 8月20日前後(旧盆)
→旧暦7月15日が新暦でいう8月20日前後のため - 8月13日~15日or16日(月遅れの盆)
→その当時は、日本国民の80%が農業を仕事にしており、新暦7月15日は農作業の多忙なシーズンに重なったため、お盆を1ヶ月遅らせて月遅れのお盆とすることで、お盆の行事をゆっくりできるようにしたため
地域によって違うお盆の期間
時の移り変わりにしたがって旧暦でのお盆が徐々に行われなくなり、現代においては約7割くらいが8月15日前後にお盆の行事を行う傾向が多くあります。
旧暦のお盆が廃れた理由として以下の3つの要因が推定されています↓↓↓
- カレンダーに旧暦の表示が載らなくなったから
- 旧暦は一年毎に変わるため把握しにくいから
- 月遅れの8月15日に固定した方がスケジュールを立てやすいから
しかしながら、旧暦でお盆の行事を行うことが減ってきたというだけで、完全にやらなくなったわけではないので、全国各地などによってお盆の時期が変わってきます。
以下に、それぞれの地域のお盆の時期を簡単にまとめました↓↓↓
- 7月13日~15日(新盆)
東京都(一部地域を除く)、南関東(主に都市部)、静岡旧市街地、函館、金沢旧市街地など - 8月20日前後(旧盆)
沖縄県、奄美など南西諸島の一部 - 8月13日~15日(月遅れのお盆)
南関東(一部地域を除く)、西日本全般と北関東以北(日本の大半の地域) - 8月1日など(その他)
岐阜県中津川市付知町、中津川市加子母、東京都(多摩地区の一部)
お盆期間は何をするの?

お盆に行うこと
- お墓参り
- お墓の掃除
- 精霊棚(しょうりょうだな)や盆棚(ぼんだな)を飾る
※精霊棚とは、お盆のみに用いられる祭壇に近いもの - 盆提灯(ぼんちょうちん)を飾る
※盆提灯とは、お盆のみに用いる装飾で、ご先祖様の霊が迷わずに帰って来られるように照らす役割があると言われているもの - 僧侶を呼んで供養の法要を行う
※特に初盆や新盆のケース - 盆会墓前読経(ぼんえぼぜんどっきょう)
※お寺によって異なりますが、お盆にお墓の前でお経を読むこと
その他では、お盆には全国各地方などによって色々な慣習を持っており、精霊流しだったり灯篭流しを行う地域もあります。
一般的に今の時代においてお盆とは、一年に一度ご先祖様の霊が家族のもとへ帰ってくる期間と言われ、迎え火を焚いてご先祖様が迷わず我が家に戻って来られるようにしてお迎えし、帰って来られたご先祖様の霊の供養を行います。
ほどなくお盆の期間が過ぎると、送り火を焚いてお送りするスタイルがお盆の慣習として定番になっていると言えます。
迎え火
迎え火とは、1日から7日に行なう地方もありますが、一般的には7月13日もしくは8月13日の夕暮れに縁側の軒先か精霊棚のところに吊るされた盆堤灯に火を灯して行います。
迎え火を行う前に、12日の17時前後や13日の午前中までに精霊棚や仏壇の装飾とお供えを終えておきます。
家の戸口や玄関で焙烙(ほうろく:素焼きの土鍋の一種)にオガラと言われている皮をはいだ麻の茎を折って積み重ね、火をつけて燃し、その場で手を合わせて合掌します。
このように、オガラを燃したその煙に乗ってご先祖様の霊が家に帰ってくるのを出迎えることを迎え火と言います。
また、お墓参りの際に、お墓で提灯に火を灯し、ご先祖様の霊を家まで誘導する地域もあるようです。
送り火
送り火とは、家に迎えたご先祖様の霊を送り火を焚いてあの世に帰ってもらうために行います。
迎え火を焚いた時と同様に、送り火を行なう際も同じ場所で16日もしくは15日にオガラをつみ重ねて火をつけ送り火を焚きます。
お盆の期間はいつ!?お盆とは何を行うもの?のまとめ
お盆の期間やお盆に何を行うのかについて参考になりましたでしょうか?
お盆休みで里帰りしてお墓参りに行ったり、お盆休みを利用して遠出や旅行をしてリフレッシュしに行くなど、様々なお盆期間の過ごし方があると思います。
お盆の行事は、その地域やそれぞれのお家によりしきたりがあったりするので、いくつもの供養のやり方があり、ご先祖様を忘れずに心から供養するという風習は素敵な伝統行事ですね。
近年では仏壇のないご家庭やお墓が遠くて中々お墓参りに行けない人も多く、ご先祖様を心から供養するという気持ちが薄れている感じがしますが、毎日が忙しく余裕がないのは別として、家系を途絶えすことなく命をつないでくださったご先祖様に、せめてお盆の期間だけでも感謝の気持ちを示す意味を込めて供養をしたいものです。